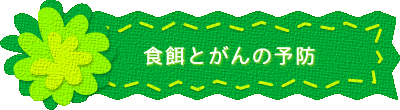|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9) 穀類 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
今までは食物の中の成分を中心としてがんとの関係を論じてきましたが、ここからはより実際に食べる食物の形で分類してそれとがん出来ればその他の病気との関係も含めて解説しようとおもいます。その主な根拠は最初に示したのと同じ国際機関の1997年の報告書です。 穀類の主なものは、われわれになじみの深いのは小麦、米、とうもろこし(コーン)などですが、その他に世界的にはキビ、モロコシ、大麦、燕麦、ライ麦などがあります。これらは何処でも主食となっています。一般的に発展途上の国では穀類が食餌の量、エネルギー共に中心となっています。それが社会の工業化が進むにつれて食物の量がへり、よりエネルギーの高いものになり、穀類もより精製され、加工されたものになっていきます。そこで穀類の消費は全エネルギーの70%から少ないところでは20%位に減ります。 穀類とその加工品は澱粉を主とし、いくらかの蛋白を含みます。その他の成分の量はその精製の度合いと処理の仕方によって変わります。線維、脂肪、ミネラル、その他の生活性物質はその大部分が胚芽に含まれていますので、精製をすると減少します。 穀類とその精製品のがんとの関係は明確ではありません。その理由は多分穀類の精製の度合いが一定せず、また穀類の豊富な食餌ではたの成分の欠乏を招きやすい、ということではないかと考えられます。ただ言えることは、全粒穀類は胃がんのリスクを下げる可能性があり、反対に極度に精製した穀類は食道がんのリスクを増す可能性があると言うことです。 なお、今では殆ど見られませんが、白米ばかり食べていると脚気に、トウモロコシばかりではペラグラ(ニコチン酸欠乏症)にばります。WHOもがん以外の心血管病などを予防するために50〜70%の種々の澱粉と一日16〜24gの食物繊維を撮ることを奨めています。 穀類とがん
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||